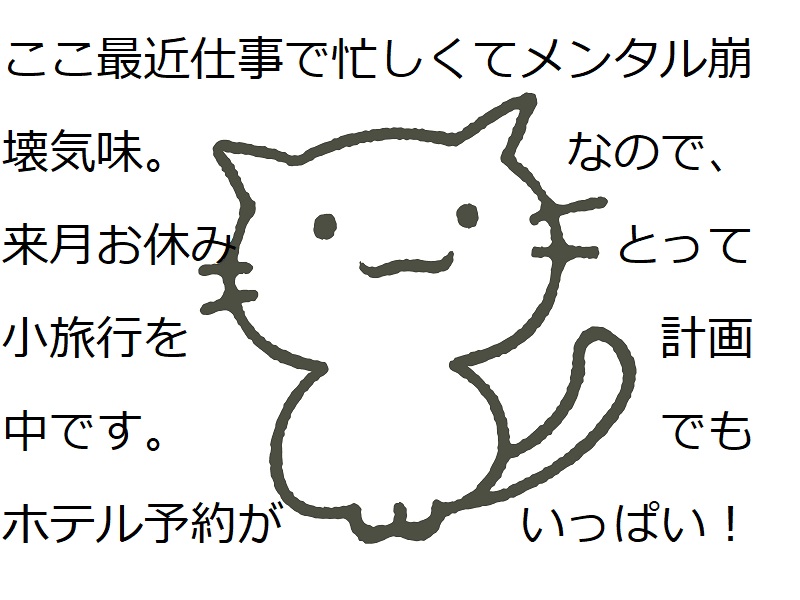こんばんは、いもみ🍠です。
本日は、『古事記』本文上巻㉝~迦具土神のその後(5)~のご紹介です。
こんばんは、アキです。
主に翻訳と解説を担当しています。
イザナギ...やっちゃいました…。
悲しみと怒りは分かるけど、我が子を殺めちゃダメでしょ…。
それにしても我が子を流したり、殺してしまったり、当時の基準では妻>子供なんでしょうか?
今回は斬られてしまったカグツチから、また神様が生まれる。そんなお話です。
イザナギ・イザナミの神生み以外にもこんなに神様が誕生していたなんて、古事記を読むまで知りませんでした。
『古事記』本文上巻㉝~迦具土神のその後(5)~
爾著 其御刀前之血 走就 湯津石村 所成神名 石拆神
次 根拆神
次 石筒之男神
(三神)
【読み方】
爾(ここに)其(そ)の御刀(みはかし)の前(さき)に著(つ=着)ける血
湯津石村(ゆついわむら)に走(はし)り就(つ)いて
成りませる神の名は、石拆(いわさくの)神
次に根拆(ねさくの)神
次に石筒男(いわづつのおの)神
(三神)
次に根拆(ねさくの)神がお生まれになりました。
次に石筒男(いわづつのおの)神がお生まれになりました。
(註:以上3柱の神々です)

「著」ですが、これは「着(つ)く」です。
「著」は「着」の本字で、「きる」「つく」として使われることがあるのです。
【本字】というのは簡単に言うと【ある漢字の元になった漢字】です。
「御刀」は「みはかし」と読みます。
※「おんかたな・おかたな」と読んでも間違いではないと思います。
意味は字のまんまですね。
この刀は「十拳劔」を指しているのは明らかですね。
「走就」は「走り就き」でしょうか。
カグツチの首をはねた時の血が、飛んで走り就いた...という事を表わしているのでしょう。
神話のお話というか、もはやホラーです。
「湯津石村」は「ゆついわむら」と読みます。
これは地名なのか場所なのか分かりませんでした。
日本書記では「湯津石村」を「五百箇磐石」と表記しています。
これを読み解くと、「五百箇」+「磐石」で、「500の岩や石がある所」。
500というのは数が多いという事を表わしていると思うので、「岩石が多い場所」。
まとめると、「湯津石村」=「五百箇磐石」=「岩石が多い場所」ということなのだろう…と勝手に納得してしまいました<(_ _)>💦
なのでここでの訳は「迦具土神(カグツチ)の首を斬り落とした十拳劔(とつかのつるぎ)の剣先に着いた血が、岩石が多い場所(湯津石村)に飛び散って走り就いた」という感じでしょうか。
・所成神名 石拆神 次 根拆神 次 石筒之男神(三神)
「石拆神」は「いわさくのかみ」と読みます。
読み通り「岩を裂く」という意味の神様...?
若しくは「拆」には「さく」の読みの他に「ひらく(=拓)」という読みがあるため、「岩や石をさいて開拓する」という意味の神様なのか…?
ちなみに性別は不明です。
「根拆神」は「ねさくのかみ」と読みます。
「根を裂く」神様ですね。
一緒に生まれた神様が「岩を裂く」神様なので、どうやら「岩と根を裂く(取り除く)」➩「開拓する」神様なのかな~…と想像しています。
こちらも性別は不明です。
「石筒之男神」は「いわづつのおのかみ」と読みます。
こちらの神様も詳細は不明で、性別も不明です。
但しここに登場した3柱の神は【経津主神(ふつぬしのかみ)】の祖先とする説もあるようです。

以上で『古事記』本文上巻㉝~迦具土神のその後(5)~のご紹介はおしまいです。
次回は『古事記』本文上巻㉞~迦具土神のその後(6)~をご紹介する予定です。
![現代語古事記 決定版 [ 竹田恒泰 ] 現代語古事記 決定版 [ 竹田恒泰 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0754/9784054050754.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1870 円
- 楽天で詳細を見る
ここまで読んで頂きありがとうございました_(..)_
※本日のおまけは一番下にあります。
お気に入りいただけたら、下のバナーをクリックしてもらえると嬉しいです。
応援よろしくお願いします📣
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村

![]()
~本日のオマケ~